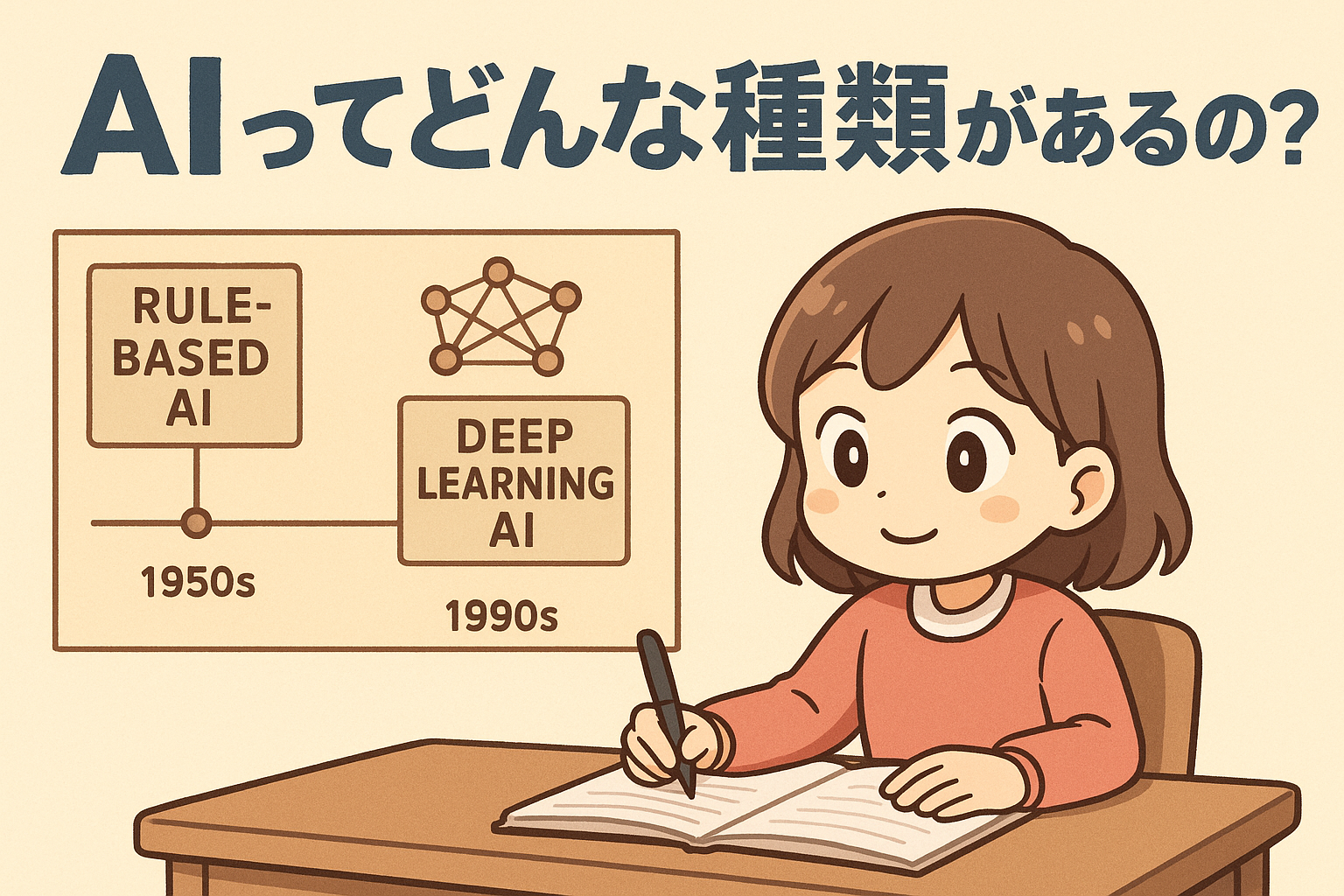最近よく耳にする「AI(エーアイ)」。
スマホのアプリ、ネット検索、カメラの自動補正、さらには自動運転まで——私たちの生活のいたるところに「AI」が登場しています。
でも、ふと立ち止まって考えてみると、「そもそもAIってなんだろう?」と思ったことはありませんか?
今回は「AI」という言葉の成り立ちから、基礎を一緒に学んでみましょう。
AIという言葉の始まり
「AI」は Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス) の略です。
日本語に直すと「人工知能」となります。
- Artificial(人工の) … 人が作り出したもの
- Intelligence(知能) … 考えたり学んだりする能力
つまり「AI=人工的につくられた知能」という意味なんです。
この言葉が生まれたのは1956年、アメリカ・ダートマス大学で開かれた会議がきっかけ。研究者たちが「人間の知能を機械で再現できるのでは?」と考え、このときに「Artificial Intelligence」という言葉が使われるようになりました。
AIは「人間の頭脳のコピー」ではない
ここでよくある誤解があります。
「AI=人間そっくりの頭脳」と思いがちですが、実際はそうではありません。
AIは人間と同じように自由に考えているわけではなく、
データを大量に学習してパターンを見つけ、判断や予測を行う のが基本です。
たとえば、AIが写真から「猫」を見分けられるのは、
何万枚もの「猫の画像」を学習し、「耳の形」「顔の輪郭」「しっぽの特徴」などをパターンとして覚えているから。
AIは人間のように「直感」で判断しているのではなく、「統計的な学習」で結果を出しているんですね。
AIが進化してきた背景
AIという言葉が登場してからすでに70年近くが経ちました。
でも、本格的に私たちの生活に広がったのはここ10年ほど。
その理由は大きく3つあります。
- コンピューターの性能が飛躍的に向上したこと
- インターネットの普及で膨大なデータが集められるようになったこと
- 機械学習・ディープラーニングといった技術が発展したこと
この3つが重なって、AIは急速に進化してきました。
まとめ
「AI」という言葉は1956年に誕生し、「人工的に作られた知能」という意味を持っています。
ただし、AIは人間のように考えているわけではなく、データを使った学習とパターン認識を得意とする存在です。
これからさらに身近になっていくAIを理解する第一歩として、まずは「言葉の成り立ち」を知っておくと、ニュースや記事を読むときもグッと理解しやすくなりますよ。
次回は、「AIってどんな種類があるの?」というテーマで、AIの分類をわかりやすく解説してみましょう!